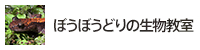◆1998年1年A組40番の課題
| 分類1 |
分類2 |
分類3 |
注 |
市町村 |
| 人物 |
男 |
着衣 |
大名行列 |
新見市 |
| 設置場所 |
設置者 |
タイトル |
作者 |
設置年 |
| 新見市内 |
不明 |
大名行列像 |
不明 |
不明 |
 |
題:「大名行列像」
場所:新見市内
これは船川八幡宮の秋季大祭で行われる、「土下座祭」つまりは大名行列に加わる武士をあらわしたものである。 |
そもそも行列は、元禄11年の秋祭りに、当時の新見藩主関氏が祭礼に参加して、敬神崇拝の高揚と領民にお安穏、五穀の豊作を祈念して、併せて家臣の屯する地域の人々に移封入国時に行った公式の「大名行列」を仕立てさせ御神幸のみぎり、その先駆の任に当たらしめたのが始まりで、以来この日の行列に限り、一般人はもちろん、御家中人といえども'下座列拝'とし、人の立拝をも許さず、下座するまで行列を止め、また行列を横切った場合は、引き返すまで前進しないという厳しい仕来りにして、百年ばかり続け、さらに廃藩後は時の岡山県令高崎五六氏から朱書の許可をもらい今日まで世代これを守って、通算300に近い回数を重ねている。
つまり、積年の伝統が、いまどき例にない'下座列拝'の歴史になったわけで、依命地区民の強い魂気と、1000戸の氏子をはじめ、一般市民の理解と協力の賜物である。