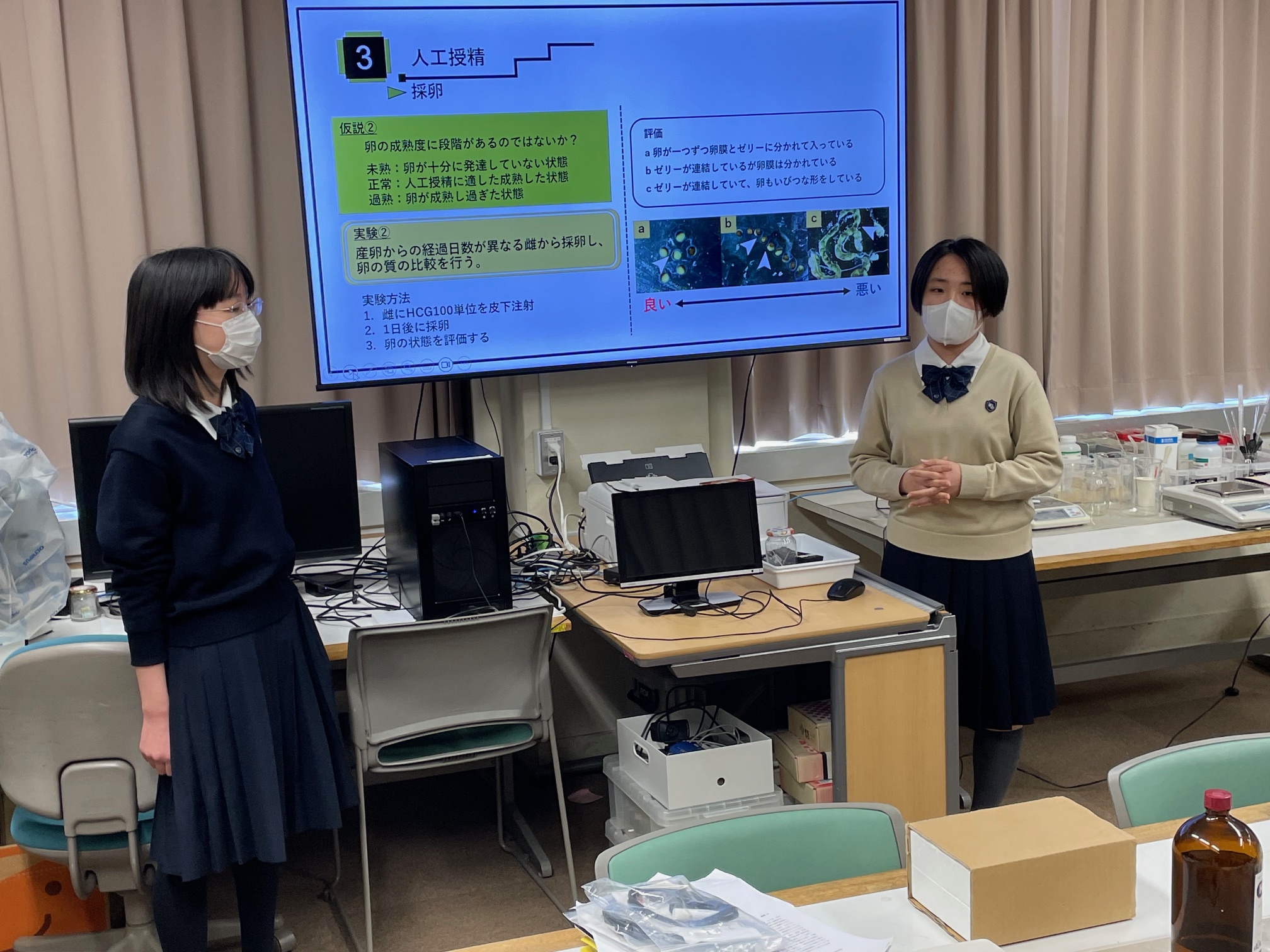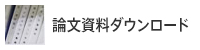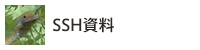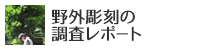自宅の机から昔(2012年6月12日購入)つかっていたKlipschのイヤフォンImage10Xが出てきたので、iPhoneに取りつけて久しぶりに使ってみた。びっくりするほど今の僕に好みの音で、ピアノの音が特に鮮明に聞こえる。オーケストラの音楽がこんな小さなイヤホンで、こんな印象になるんだと再認識した。
IMAGE10Xの能力を再発見するとともに、大学を65歳で退職するまで、バタバタと忙しく日々を過ごしていて、ゆっくり音楽を聴くことがなかったとも再認識した。昨年春に宮崎から東京に仕事を異動したが、昨年7月に心臓を患って入退院を余儀なくされた。これまでのように、スポーツもバイクも楽しめなくなってしまったのだ。やっと、奇跡的な回復したといえど、半年後の1月30日にやっと交通機関での移動が認められた程度である。
来月(5月)の検診で心臓の収縮率が40%(正常者は65%、心不全発症時は22%)に回復していれば、突然死防止も人工心臓移植を相談されることがなくなる予定だが、これまで、入浴制限、減塩の食事などの健康を考えた節度ある生活が求められてきた。
この半年間で、自分を救ってくれたのは、音楽とU-NEXTのドラマの鑑賞だった。
クラシックを毎日(朝起きて朝食を食べるまで、夜寝床に入って寝るとき)聞く習慣は、今回の治療期間に身につけた習慣である。これからも、生活を楽しむためにも継続したい。