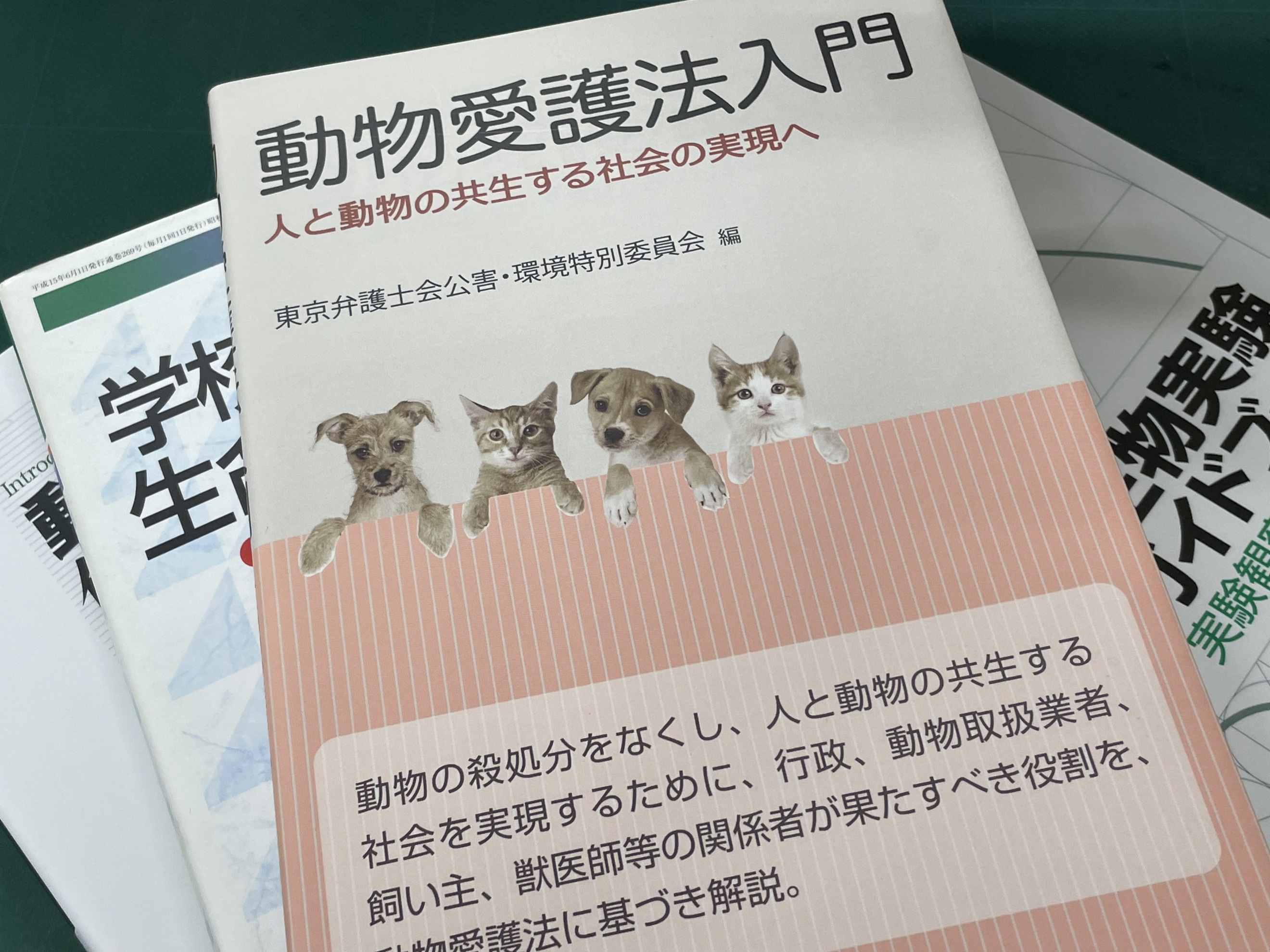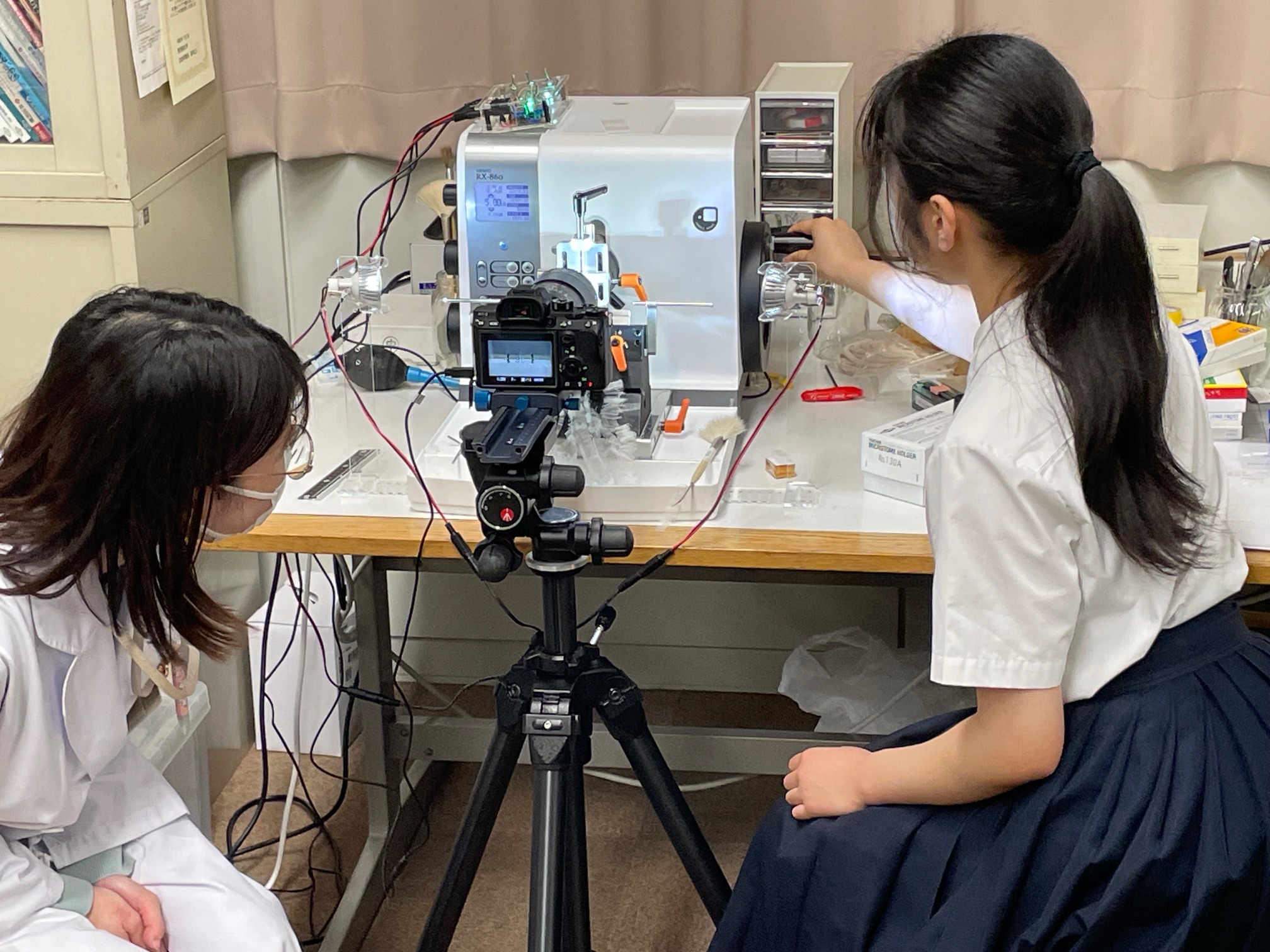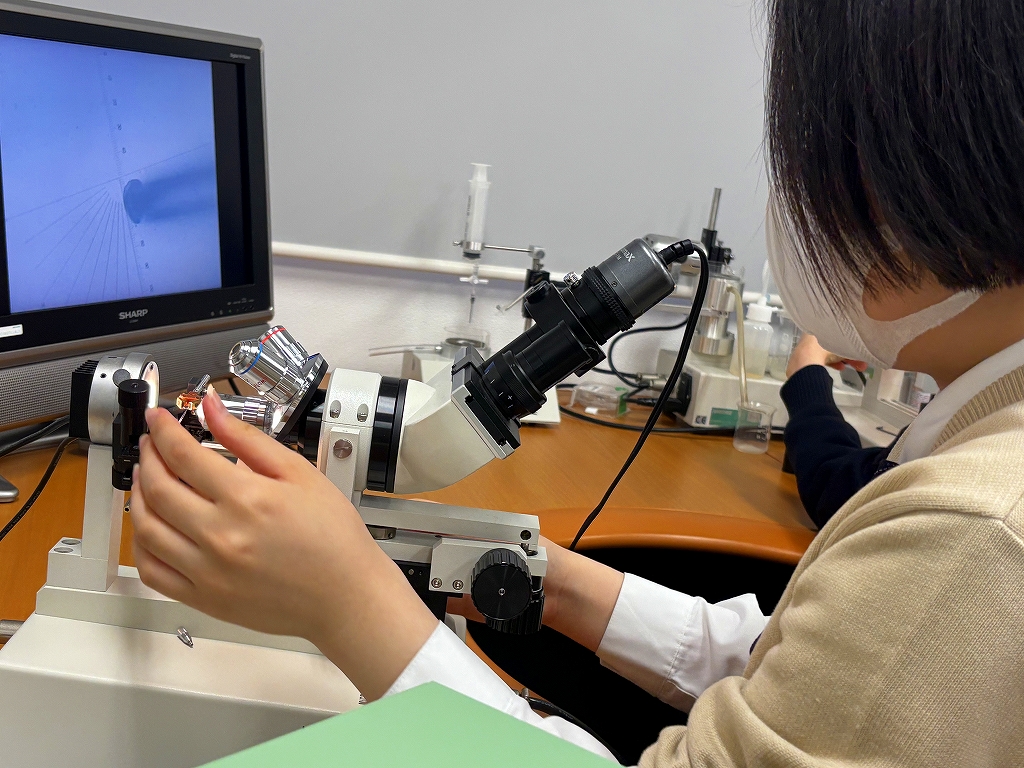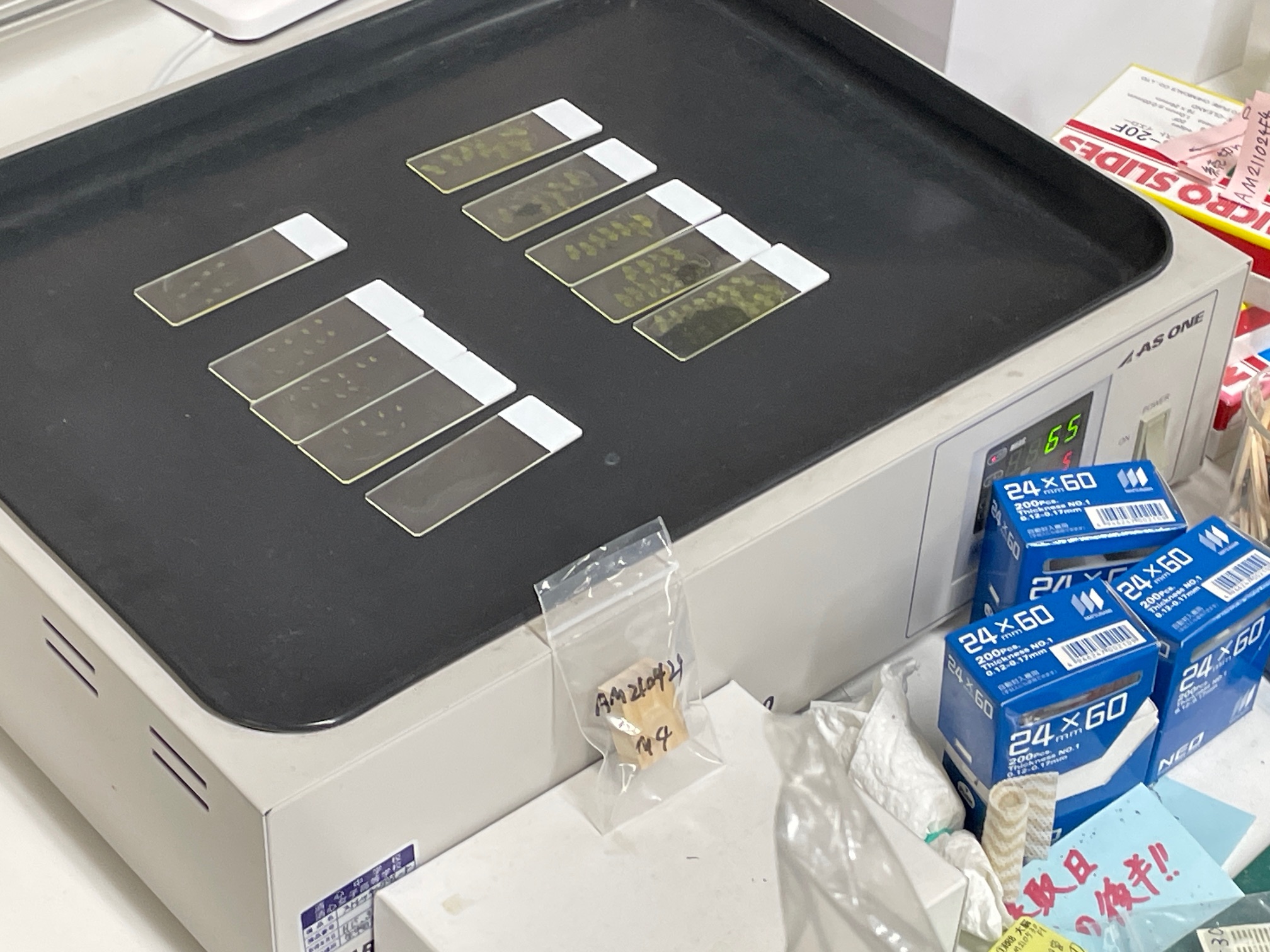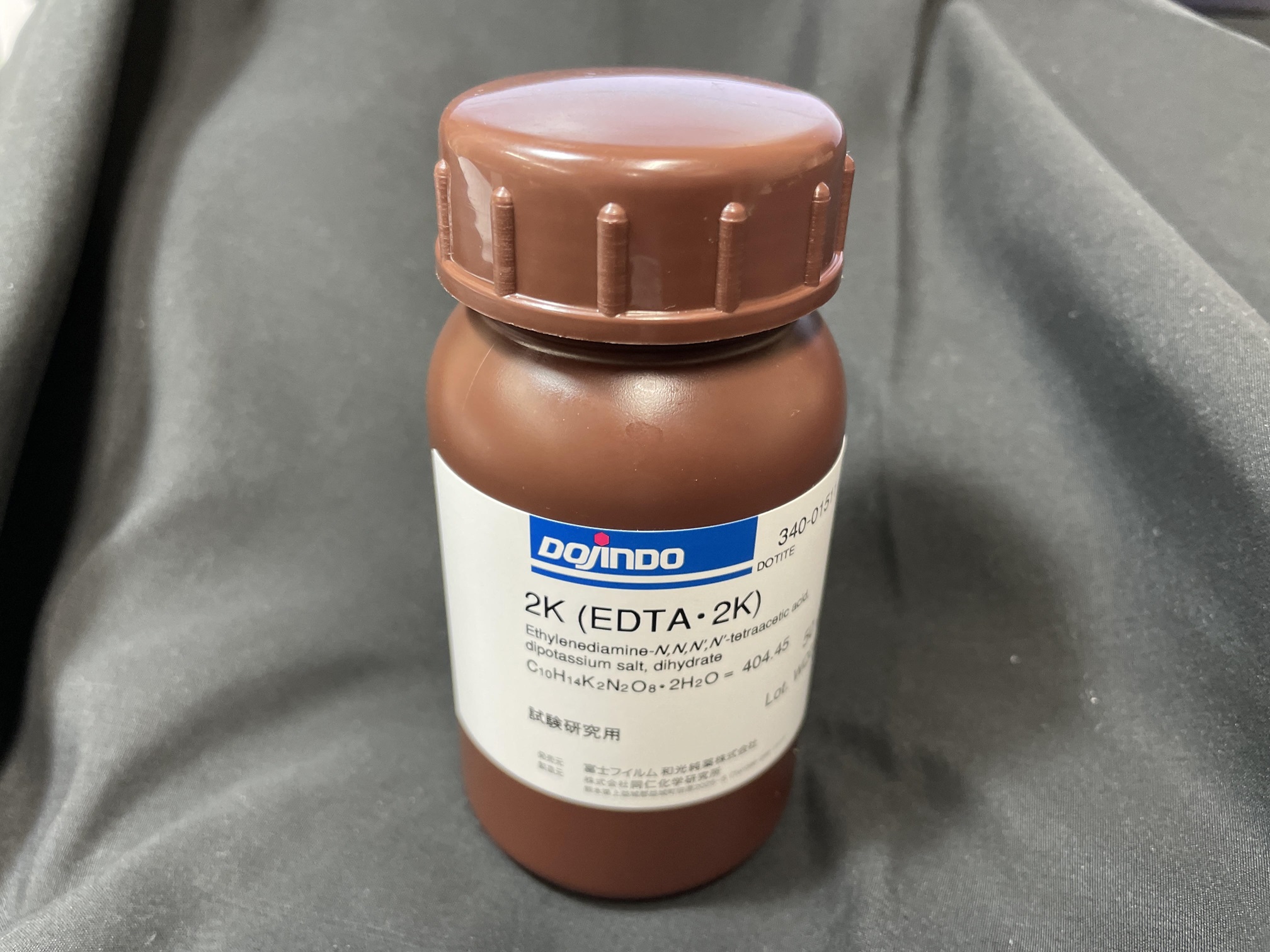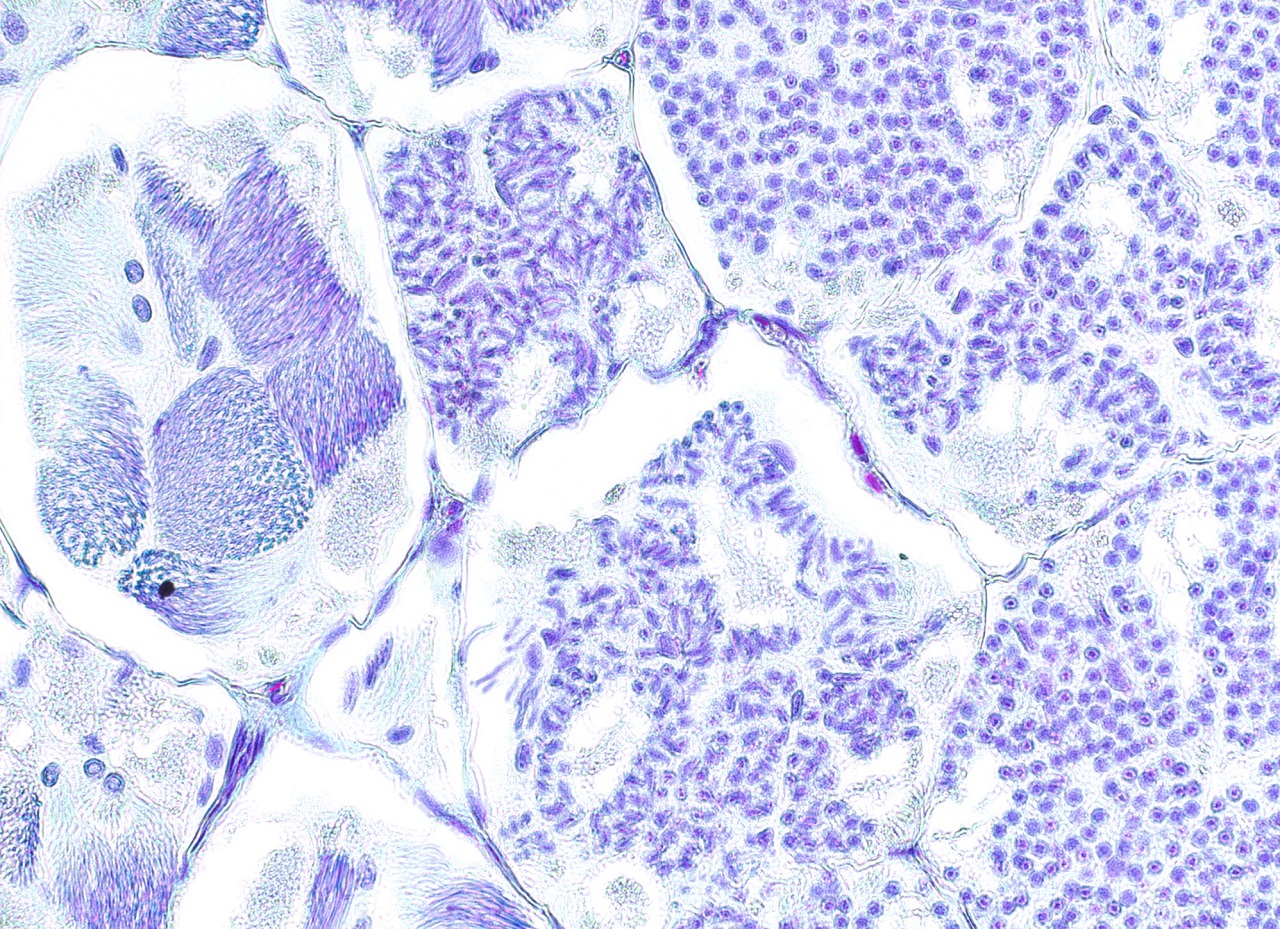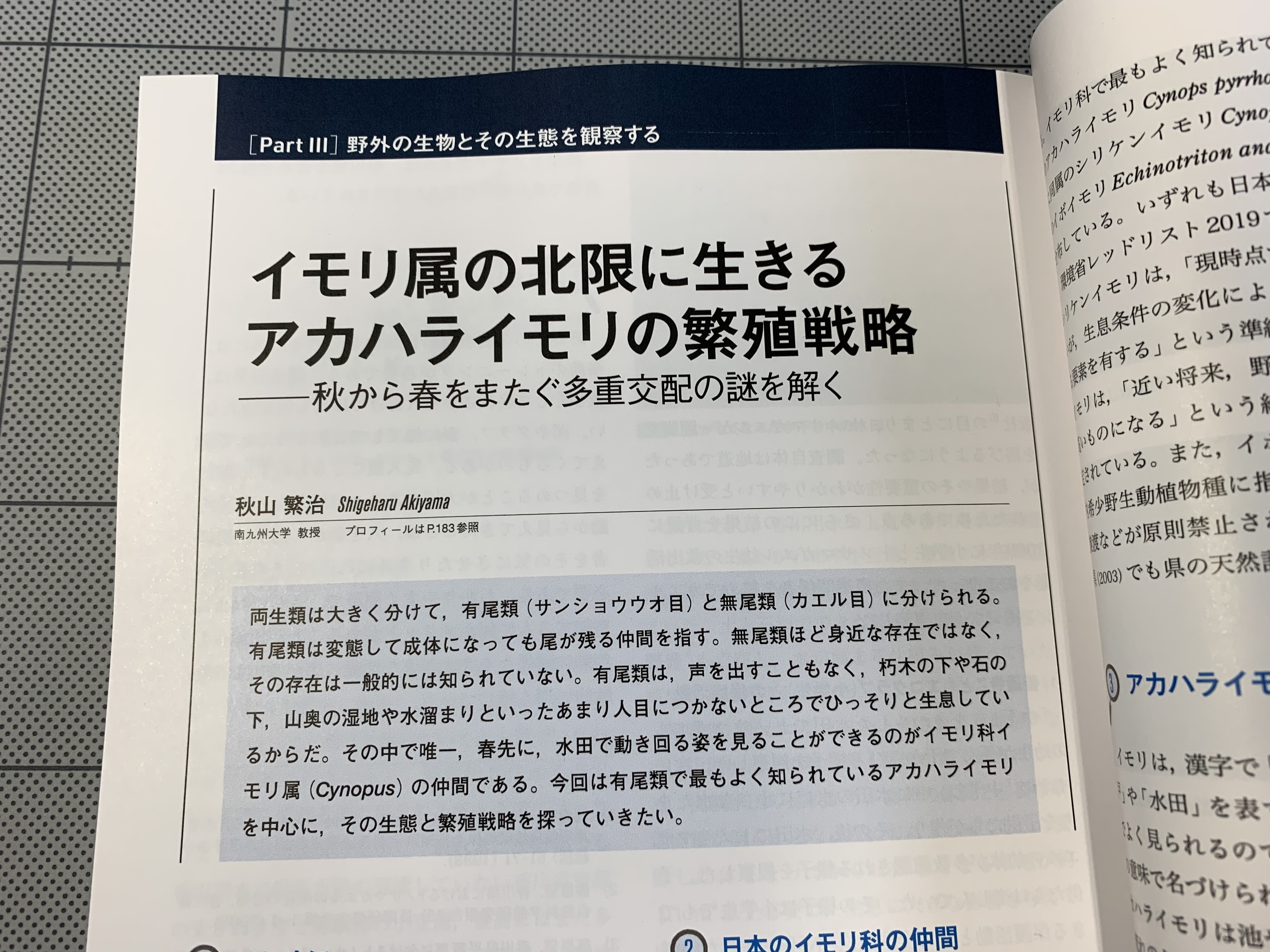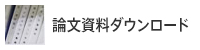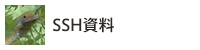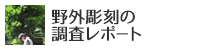2024年4月1日から施行されている「学校法人山脇学園動物実験規程」を所長として公開させていただきます。内容についてのご意見があれば、より適切な規定になりように参考にさせていただきます。
(目的 )
第1条 この 規程 は、学校法人山脇園 (以下、本学という。)山脇 有尾類研究所(以下、研究所という。) における動物実験等を適正に行うため、関連法令により動物実験委員会の設置、動物実験計画承認手続き等の必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次各号掲げる用語定義はそれぞ当該各号に定めるところによる。
(1)「動物実験等」とは、第5号に規定する実験動物を理科教育及び科学課題研究の利用に供することをいう。
(2)「飼養保管施設」とは、実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設(研究所研究室及び飼育室・生物教室など)をいう。
(3)「実験室」とは、実験動物に実験操作を行う動物実験室をいう。
(4)「施設等」とは、飼養保管施設及び実験室をいう。
(5)「実験動物」とは、動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類及び魚類に属する動物をいう。
(6)「動物実験計画」とは、動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7)「動物実験実施者」とは、動物実験等を実施する者をいう。
(8)「動物実験責任者」とは、動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者(申請者)をいう。
(9)「実験動物管理者」とは、校長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する者をいう。
(10)「飼養者」とは、実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(11)「管理者等」とは、校長、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。
(12)「法令」とは、法、飼養保管基準、その他動物実験等に関する法令(告示を含む)をいう。
(13)「指針等」とは、基本指針及び動物実験等に関して行政機関の定める基本指針並びにガイドラインをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、本学において実施される実験動物の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。
2 前項で定めた以外の動物を用いた動物実験等においても、この規程の趣旨に沿って実施することを原則とする。
3 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の第三者に委託等する場合、委託先においても、指針等に基づき、適切に動物実験等が行われることを確認するものとする。
(組織)
第4条 校長は、本学における動物実験等の適正な実施、実験動物の飼養及び保管に関する最終的な責任者として、者として、本学における動物実験等の適正な施並び飼 者として、本学における動物実験等の適正な施並び飼 者として、本学における動物実験等の適正な施並び飼 者として、本学における動物実験等の適正な施並び飼 者として、本学における動物実験等の適正な施並び飼 養及び保管を統括する 養及び保管を統括する 養及び保管を統括する 養及び保管を統括する 養及び保管を統括する 。
2 校長は、動物実験計画の審査、実施状況及び実施結果に関する助言、飼養保管施設及び実験室の調査、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、第5条および第6条に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(動物実験委員会の役割)
第5条 動物実験委員会(以下、委員会という。)は、校長の諮問を受け、次の事項を審査又は調査し、校長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画が法令及び指針等並びにこの規程に適合していることの審査
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3) 施設等の設置及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに法令及び指針等に関する教育訓練の内容、又は動物実験にかかわる学内体制に関すること。
(5) 動物実験にかかわる自己点検・評価及び外部検証に関すること。
(6) その他、動物実験等の適正な実施のための必要な事項に関すること。
(委員会組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 1~2名
(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 1~2名
(3) 本学教員 1~2名(うち1名は理科教員)
2 前項各号に掲げる委員は、校長が選任する。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の審議については、その経過及び結果の概要を記録した議事録を作成する。
(委員長等)
第7条 委員会に委員長を置き、前条第1項各号に掲げる委員の中から、委員の互選により選出する。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときは、校長は、委員を補充選任するものとする。この場合において、補充選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(動物実験計画の立案、審査、手続き)
第9条 動物実験責任者は、次の各号に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、所定の「動物実験計画申請書等」を校長に申請する。
(1) 研究の目的、意義及び必要性に関すること。
(2) 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。
(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種、個体数及び飼養条件を考慮すること。
(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
(5) 苦痛度の高い動物実験等では、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイントの設定を検討すること。
2 校長は、動物実験等の開始前に動物実験責任者に動物実験計画を申請させ、委員会の審査を経て、申請を承認し、又は却下するものとする。
3 委員会は、前項の審査の過程において、必要に応じ、動物実験責任者に対し助言を与え又は 実験計画を修正させるなど、校長に報告又は助言する前に、必要な措置を講ずることができるものとする。
4 校長は、第 2 項の審査結果を、所定の「審査結果通知書」により動物実験責任者に通知する。
5 動物実験責任者は、動物実験計画について校長の承認を得た後でなければ、動物実験等を行ってはならない。
(実験操作)
第10条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法令及び指針等に則するとともに、特に以下の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項に関すること。
(3) 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用に関すること。
(4) 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮に関すること。
(5) 適切な術後管理に関すること。
(6) 適切な安楽死の選択に関すること。
(7) 安全管理に注意を払うべき実験については、法令に従うこと。
(8) 実験実施に先立ち、必要な実験手技等の習得に努めること。
2 動物実験責任者は、動物実験計画を変更しようとする場合は、所定の「動物実験等計画変更申請書」により変更内容について校長に届け出なければならない。
(実験結果の報告)
第11条 動物実験責任者は、動物実験計画書に基づき、動物実験等を実施した後、所定の「動物実験等(終了・中止)報告書」により、使用動物数、動物実験計画からの変更の有無、成果等の、動物実験計画の実施結果について校長に報告しなければならない。
2 校長は、動物実験計画の実施の結果について、委員会に報告する。
3 校長は、動物実験計画実施の結果について、必要に応じ委員会の助言を受け、適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずるものとする。
(マニュアルの作成と周知)
第12条 管理者及び実験動物管理者は、飼養保管等のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させるものとする。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第13条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めるものとする。
(実験動物の導入)
第14条 管理者は、実験動物の導入に当たり、法令及び指針等に基づき適正に管理されている機関から導入するものとする。
2 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講ずるものとする。
(飼養及び保管の方法)
第15条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うものとする。
(健康管理)
第16条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行うものとする。
2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行うものとする。
(異種又は複数動物の飼育)
第17条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養及び保管する場合、その組み合わせを考慮して収容するものとする。
(記録管理の適正化及び報告)
第18条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備、保存するものとする。
2 管理者は、年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類と数等について、動物実験に関する自己点検・評価報告書にて校長に報告するものとする。
(譲渡等の際の情報提供)
第19条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養又は保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供するものとする。
(輸送)
第20条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めるものとする。
(飼養保管施設の設置)
第21条 飼養保管施設を設置する場合、管理者は「飼養保管施設設置承認申請書」を提出し、校長に申請するものとする。
2 校長は、申請された飼養保管施設等を委員会に調査させ、その助言により、申請を承認し、又は却下するものとする。
3 管理者は、校長の承認を得た飼養保管施設等でなければ、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に飼養若しくは保管又は動物実験等を行わせることができない。
(飼養保管施設等の要件)
第22条 飼養保管施設等は、以下の要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
(2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床や内壁などの清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(6) 実験動物管理者が置かれていること。
(実験室の設置)
第23条 飼養保管施設等以外において、実験室を設置する場合、動物実験責任者が所定の「実験室設置承認申請書」により、校長に申請するものとする。
2 校長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、申請を承認し、又は却下するものとする。
3 管理者は、校長の承認を得た実験室でなければ、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に実験動物への実験操作を行わせることができない。
(実験室の要件)
第24条 実験室は、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1)実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2)排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
(3)常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第25条 管理者は、実験動物の適正な管理、動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めるものとする。
2 管理者は、実験動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境を確保するものとする。
(施設等の廃止)
第26条 施設等を廃止する場合、管理者は、所定の「施設等廃止届」を校長に届け出るものとする。
2 校長は、廃止届出された施設等を委員会に調査させ、その報告により、廃止を承認するものとする。
3 前項に基づいて届け出た管理者は、廃止する当該施設等に飼養又は保管中の実験動物があるときは、動物実験責任者と協力して、必要に応じて、他の飼養保管施設等に譲り渡すよう努めるものとする。
(危害防止)
第27条 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接することのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(教育訓練)
第28条 校長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に対し、以下の各号に掲げる事項について、教育訓練を実施するものとする。
(1) 法令、指針等、本学の定める規程等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 安全確保、安全管理に関する事項
(5) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
2 前項に基づいて教育訓練を行ったとき、校長は、下の各号に掲げる事項を記録し、学校法人山脇学園文書処理規程に定める期間、その記録を保管する。
(1) 実施日
(2) 訓練内容
(3) 講師氏名
(4) 受講者氏名
(自己点検・評価・検証)
第29条 校長は、委員会に毎年、基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し、自己点検・評価を実施するよう指示するものとする。
2 委員会は、前項に定める校長の指示に基づき、動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を校長に報告しなければならない。
3 委員会は、前項に定める自己点検・評価を行うときは、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者及び管理者に対して、必要に応じて、関係資料を提出させることができる。
4 校長は、自己点検・評価の結果について、可能な限り、外部の機関等による検証を実施するよう努めなければならない。
(情報公開)
第30条 校長は、本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管状況、動物実験にかかわる自己点検・評価、外部の機関等による検証の結果を毎年1 回程度公表する。
(準用)
第31条 第3 条第2 項に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等に供する場合においても、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
(準拠)
第32条 本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の適正な飼養及び保管に関する具体的な方法は、ガイドラインに準拠するものとする。
(その他)
第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附 則
1)この規程は、令和6年4 月1 日から施行する。