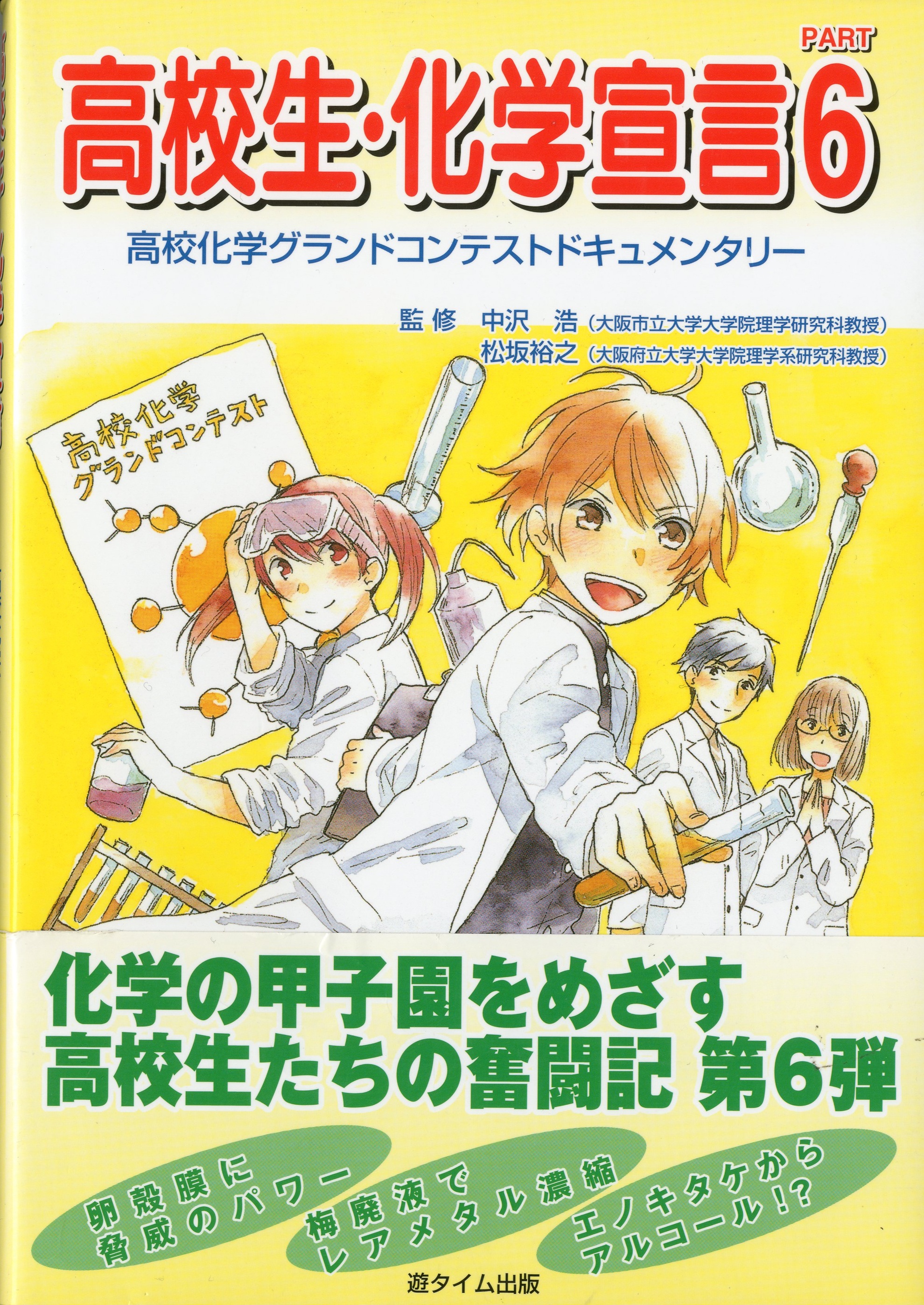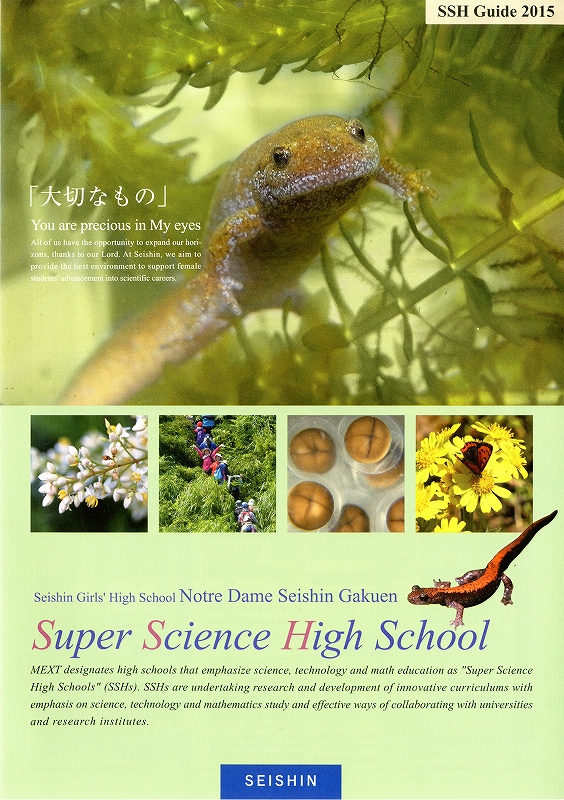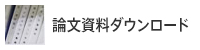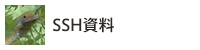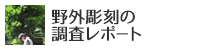2003年7月にシングル発売され、フジテレビ系ドラマ『Dr.コトー診療所』の主題歌として書き下ろされた曲。離島医療を描くドラマの世界観に合わせ、「絶望の海を越えてでも、助けに行く」といった"救い"を主軸に据えて作詞したと中島みゆきが語っています。
龍は、漢詩や神話で龍は雲を呼び雨を制する守護的存在で、海と空の境界線を一気に飛び越える"銀色の龍"は、「困難を貫いて希望を運ぶ架空の乗り物」の象徴ので、その「背に乗る」という表現で"弱き者を乗せて高みへ連れて行く"ことを表現しています。
歌詞の「(人に)柔らかな皮膚しかない訳は、人が人の傷みを聴くためだ」には、「弱さ」が共感能力の源泉であり、このドラマには「医師が患者の痛みを共感する存在でなくてはならない」というメッセージが込められています。これは医者に限らず、人であれば誰しも大切にしなければならないことで、今の私のような定年を過ぎても高校生の教育に関わっている人間にも必要なことだと思います。
「銀色の龍」について調べると、「銀色」は、潜在能力、直感、感受性、洞察力などを象徴し、内面の成長や精神的な発展をもたらすと言われ、また、「龍」については、非常に洞察力があり、深い直感を持つとされ、人々の心の内側を見抜くことができるとも言われています。 天の存在であり、空や天界の守護者として崇められ、自然界の力を司り、水や雨を与え、風を呼び起こし、地球の生命力を支配しています。知恵や癒しの象徴とも言われています。
海と空の境界線を一気に飛び越える「銀色の龍」は、「困難を貫いて希望を運ぶ架空の乗り物」の象徴であり、「背に乗る」という言い回しは弱き者を乗せて高みへ連れて行くことに繋がっているのです。
ドラマ『Dr.コトー診療所』は、テレビで第一シリーズが2003年7月、第2シリーズが2006年10月~12月に放送されました。それとは別にスペシャルが2004年11月が放送され、映画が2022年に公開されました。
あらすじは、東京の大病院に勤務していた外科医・五島健助(通称:コトー先生)が、ある事情で都会の医療現場を離れ、高齢者が多い典型的な過疎の島「志木那島」の診療所に赴任し、島民から「都会の医者が長くもつわけない」とみられながらも、誠実で丁寧な医療姿勢と高い技術力で信頼を得ていくというものです。
高視聴率が高かったので、シリーズ化されましたが、医療関係者や離島医療に関心を持つ学生にも影響を与え、実際に医師を志すきっかけになったという話もあります。私も全シリーズ、スペシャルも映画も楽しませていただきました。
2022年の映画で「銀の龍の背に乗って」が再び主題歌に使われ、原点回帰となる作品になっていました。「現代における理想の医師像」を描いたと評価されましたが、学校教育に従事する私も医師としての姿勢(人への向かい方)から多くを学ばせていただきました。
『銀の龍の背に乗って』を聞くと勇気をもらったような気持ちになるのですが、不思議な詞だと感じていました。もう一度、聞いてみてください。聞きながら、どんな風景が思い浮かぶでしょうか。上の写真は、ファイピン最後の秘境、パワラン島を2025年5月30日に訪問した時の風景です。