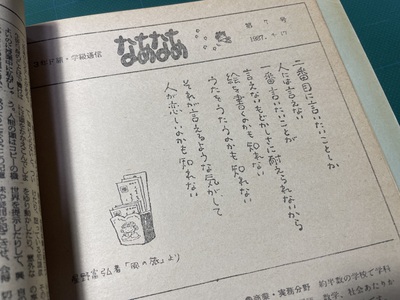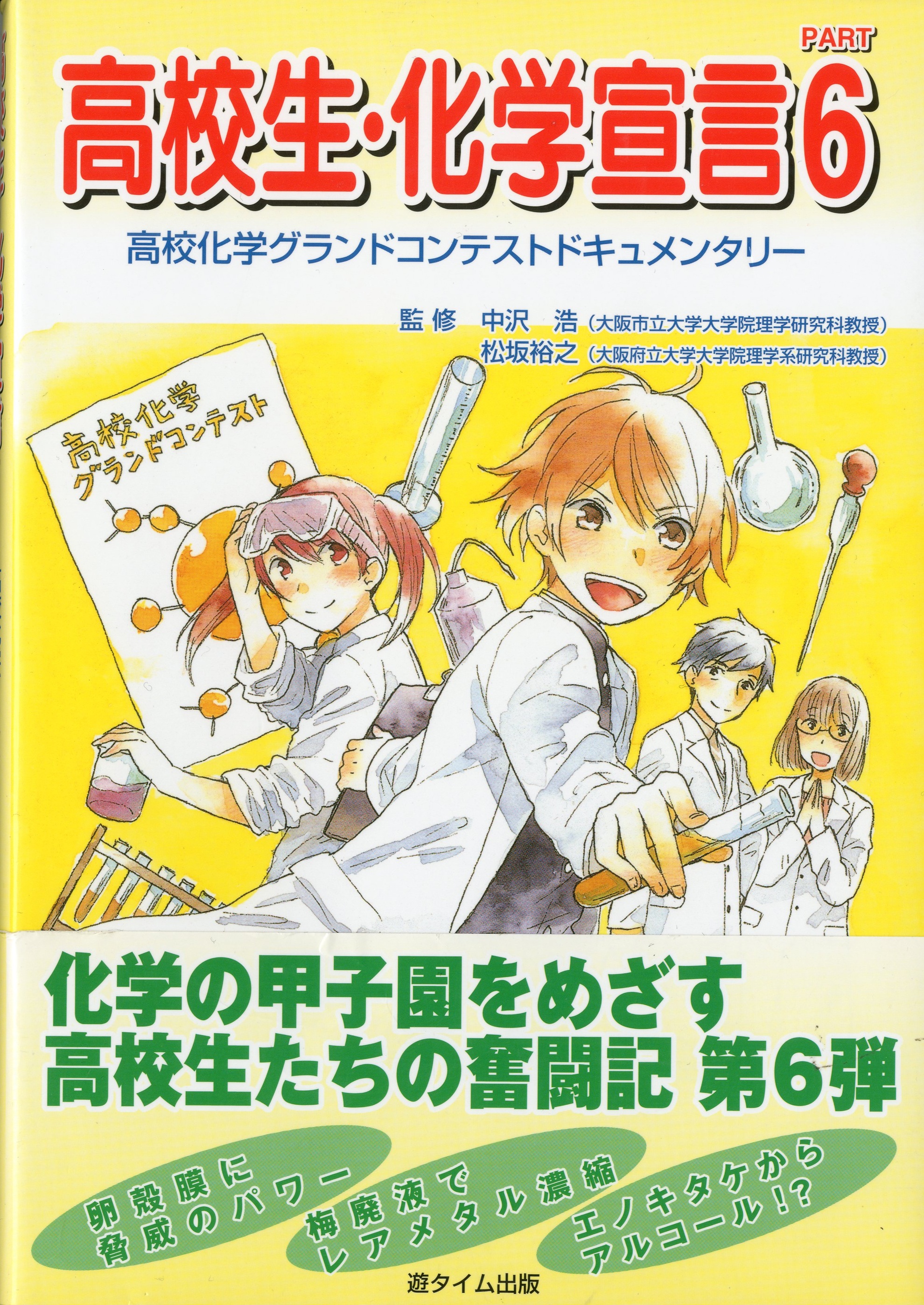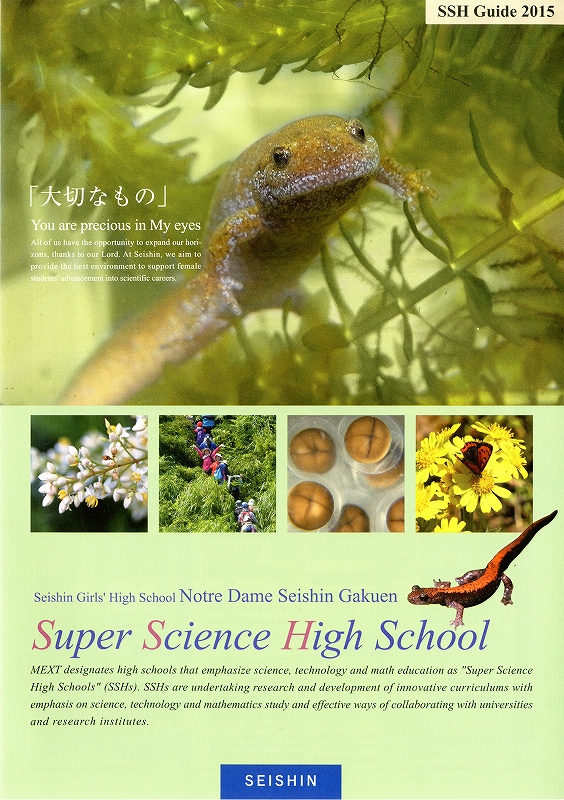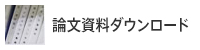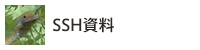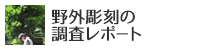尾崎放哉(おざき ほうさい)は、1885年(明治18年)に鳥取県鳥取市に生まれ、高校時代から句作を始め、校友会雑誌に俳句や短歌を残している。第一高等学校で夏目漱石に出会い、「一高俳句会」に入会、夏目漱石に師事。
この頃は伝統俳句が多く、「ホトトギス」への投句も行っていた。「一高俳句会」で荻原井泉水に出会い、大学卒業後は無季自由律俳句を詠むようになった。「層雲」に投句を始めて頭角を表し、種田山頭火と並ぶ自由律俳句の代表的な俳人となった。
1923年に無所有を掲げる「一燈園」に入ったことをきっかけに、極貧生活を送り、句作に没頭。孤独を詠む句が多くなった。1925年に香川県にある西光寺南郷庵に入庵するが、翌1926年(大正15年)に肺病で亡くなっている。西光寺に墓地がある。
「咳をしてもひとり」は自由律俳句の代表としても取り上げられる句である。
ひとをそしる心をすて 豆の皮をむく
私としては、この句がしっくりと心に染み入った。
この句をよんで、ふと、1986年6月9日に発行した学級通信「風の谷」に掲載した花田英三の詩を思い出した。
豆
豆を喰いながら
なにかかんがえるつもりでいたが
ふと気がつくと
おれはいっしんに豆をくっていた
豆を食べていると、いつの間にか無心に食っていて、我を忘れている自分に気が付く。「ひとをそしる心」も同じく消えていたのだろうか。
無心になって考えるのをやめて、思考の外側に追いやりたいのに頭にこびり付いて離れない煩悩が多いから、「豆を喰う」ことも「豆をむく」こともささやかな気分転換になるのかもしれません。
※学級通信(クラス担任として、できるだけ毎日発行するつもりで取り組んだわらB4判一枚のプリント)
学級通信は、今から約40年前に高等学校のクラス担任をしていて、なんとか生徒に自分の考えを知ってもらおうと考えて発行したものである。以下は、その思い出を、このHPの2015年3月9日の「"ぼうぼうどり"って呼ばれた時代もあったね。」で語っている。以下は抜粋です。
私が学級通信を初めて出したのは1983年7月13日、この学校に最初に勤めて、高校一年生を担任した時です。赴任してから三か月過ぎた頃、自分の考え方と生徒の考え方が正面からぶつかる状況が続いたことがありました。その時、それをなんとか解決したい、自分を理解して欲しいという気持ちから一号・二号の学級通信をだしたのを今でも憶えています。しかし、結果として、自分を理解されるどころか、自分が書いた通信がゴミ箱に捨ててある状況、つまり、まったく価値を認めないという返事が返ってきたのです。何日もかけて自分の伝えたいこと書いたのに判ってもらえない。そして、自分自身も理解させる力がないこと痛切に感じました。その後、通信はしばらく出しませんでした。そして、再度三学期には、とにかく捨てられても良いから、自分も楽しめる、つまり、自分が楽しみながら得たものの一部を紹介していくことも含めて始めることにしました。その時、次の文をつけて出しました。
=この通信をだすことへの弁解=
いままで二回〝ぼうぼうどりという通信をだしました。出した時の理由は、その時の自分が何かすべて自分が思うようにならない、なんとかしたい。そんな思いだったと思います。勝手と言えば勝手で、そのあげくに「もう、読まないから」といい意見を取り入れて止めてしまいました。自分自身の「どうせわかりっこないし」という気持ちも止めることを正当化していたと思います。でも、なにかしら、心の山奥の方で、これでいいのかなぁという気がして、やっぱり一度やろうと決めたことは最後まで試行錯誤しながらでもやらなければ、という気になったのです。担任がくじけているのに「生徒だけ、頑張れ!!」と言ってもやっぱり、どこかおかしい気がするし、これが最低の義務だと思うのです。
それ以後、学級通信を出すことを自分に課すことになりました。それから、1984年度「ゆにこーん」、1985年度「ぼうぼうどり」、1986年度「風の谷」、1987年度「なあなあ」(途中中断)と続けてきました。一年間に多いときは200号、少ないときは28号、内容は、気にいった詩、問題を投げかけてくれた新聞記事、本からの抜粋が中心で、その他学級での出来事、自分の感想といったものでした。ここで、何故気にいった詩、新聞記事、本の抜粋を中心にしたかというと次のような自分の考え方があるからです。
普通、学校であたえる授業の教材・同和教育・性教育の資料にしても何かしらのかたちでまとめや感想を要求するわけですが、それがあると、どうしても〝やらされる″という負担感をもってしまう。だから、べつに意識しなくていい、つまり″使い捨て〟の考える材料として学級通信を出したかったと言うことがあるのです。
私の考えですが、それぞれの人が持っている感受性とか考え方の多くは、意識されないでなんとなく過ごした時間の中でつくられてくるような気がするのです。生徒についてもほんとうに影響を及ぼすのは、計画された○○のH・Rの時間や教師の一過性の説教ではなく、学校全体を流れる雰囲気だ思うのです。
そして、私の読書遍歴は、その学級通信をだしていた五年間についてはその通信の中にすべて含まれてしまったのです。そして、自分の接してきた文章、詩などをどんどん紹介していきました。一つの文、一つの詩を具体的に決めていくとき、自分の気持ちが整理できるような気がして、作業を続けていきました。しかし、二年目に入り、毎日だすだけの資料が不足し出したのです。本当に納得したものがない状況になり、自分の読書が通信をだすためだけのものになってしまったの感じだしたのです。自分自身で蒔いた種ではありますが〝やらされる読書"としての負担を感じだしたのです。楽しんでだしていた時はまったく感じなかったものが、〝通信の為に読まなければ″という気持ちが出てくるとともに、読書そのものも嫌になってきたのですその年はとにかく200号だせましたが、次の年から毎日だすということが出来なくなりました。「とにかく、頑張りたい。」という気持ちでやってみましたが、結局6年目で止めました。