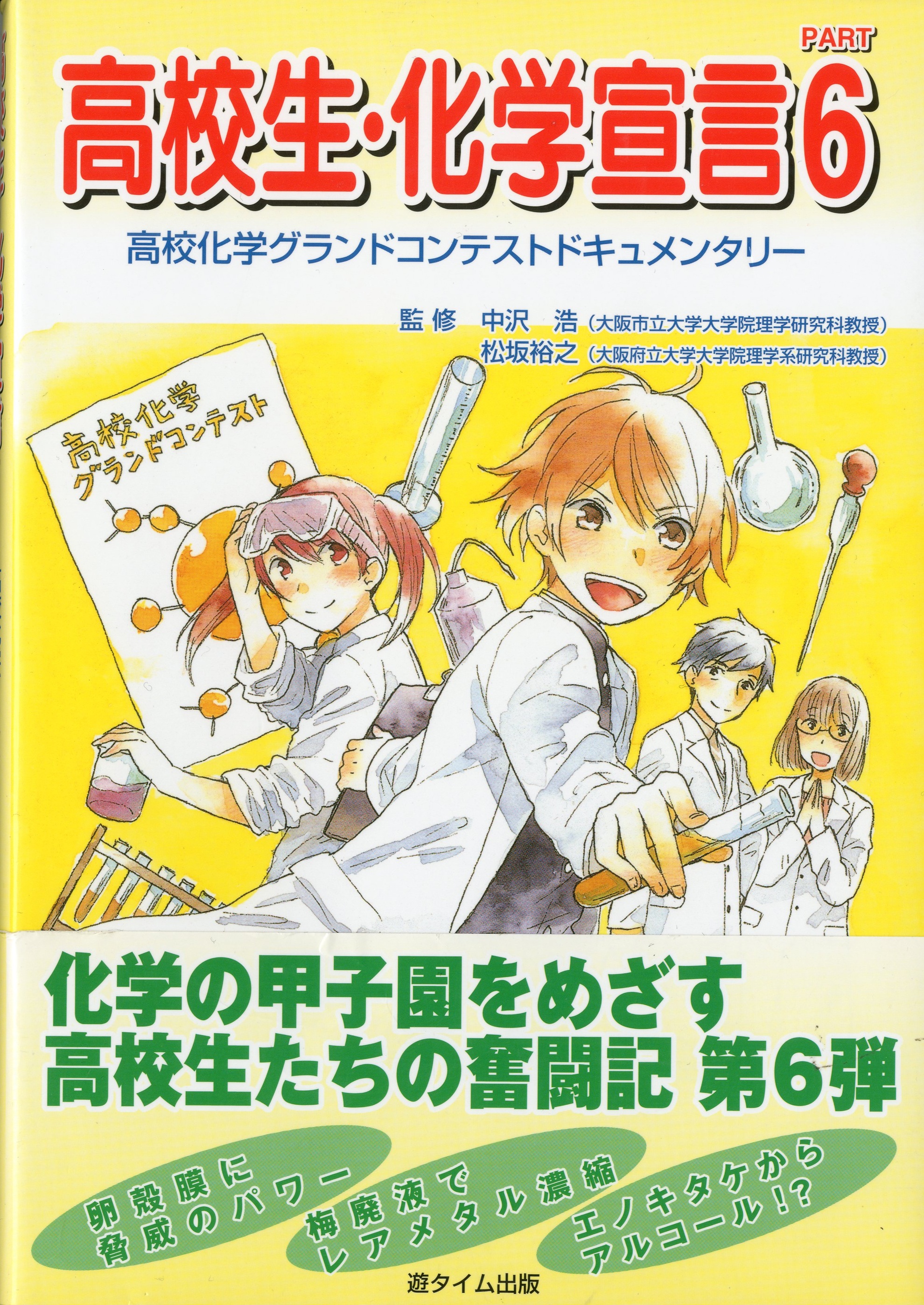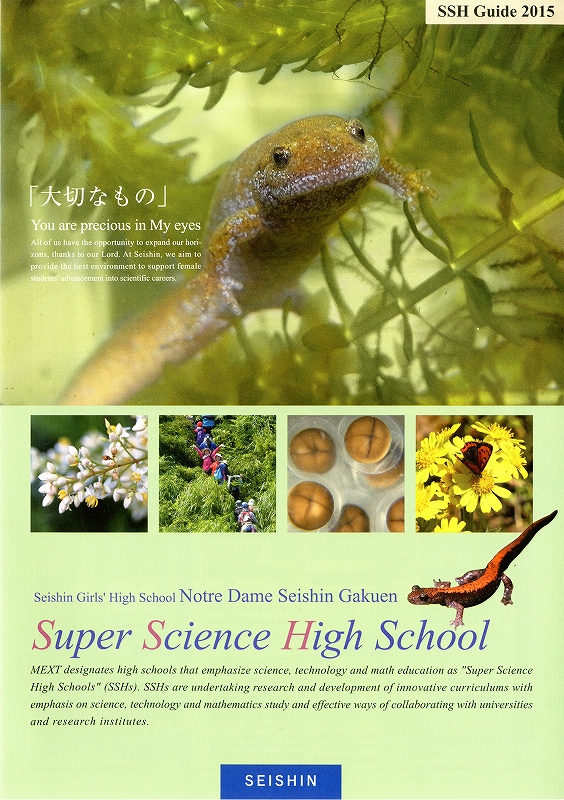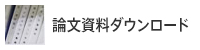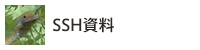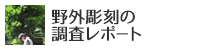日本郵便で、配達中にバイクで事故を起こした配達員に対し、罰として自転車での配達を強制する「懲罰自転車」という処分が、長年にわたって行われていたことが明らかになった。
この「懲罰自転車」は、事故を起こした者に対する"見せしめ"の意味合いが強く、「事故を起こすとひどい目に遭うから気をつけろ」という威嚇的な意図で運用されていた。自転車を漕ぐことでバイクの運転技術が向上するわけではなく、実質的には「懲らしめるため」の処分でしかなかった。
処分を受けた配達員は、自転車でバイクと同じ量の郵便物を配達することを原則とされ、真夏の猛暑など過酷な環境下でも強制的に業務を行わされたという。ある元配達員は「昔からやっていたから、みんなもそうしてきた」という理由で拒否できない状況が会社によって作られていたと証言している。物損事故で三度の「懲罰自転車」を経験し、最長で三か月に及んだこともあったという。また、管理職も局長の指示で「懲罰自転車」を科された同僚を点検し、「合格かどうか見てこい」と命じられることがあった。
正社員でない場合、処分を拒否すれば契約を打ち切られ、「期間が来たら辞めろ」と言われることもあったという。日本郵便では、世間の常識と自社の常識にずれがあっても、「自分たちの当たり前」を優先する体質が根強く残っている。
これは日本郵便という組織の旧態依然とした体質を象徴する問題であり、見直しが進まず、長年の慣習がそのまま続いてきた実態の一端を示している。日本郵便への取材によると、同社は「合理性が認められず、また認識に齟齬が生じることがないよう、懲罰またはハラスメントと受け取られかねない行為については、今月14日付(2025年10月14日)で禁止する旨の周知を行った」と回答している。
郵政民営化から約20年が経過したが、実質的には体質がほとんど変わっていない。社会は急激に変化し、はがきや年賀状の利用が激減する中でも、民営化後の日本郵便という巨大組織は依然として旧来の文化にとらわれ続けている。その背景には何があるのだろうか。
ある意味で、このような慣行もまた、「治安がよく、経済的にも安定している」という日本社会特有の安心感の裏側に潜む、日本的な組織文化の一端を映し出しているのかもしれない。
(記事は2025年10月30日yahooニュースから要約して、意見を具申。写真は我が愛車ヤマハTMAX、2014年5月~2023年2月まで9年間使用)