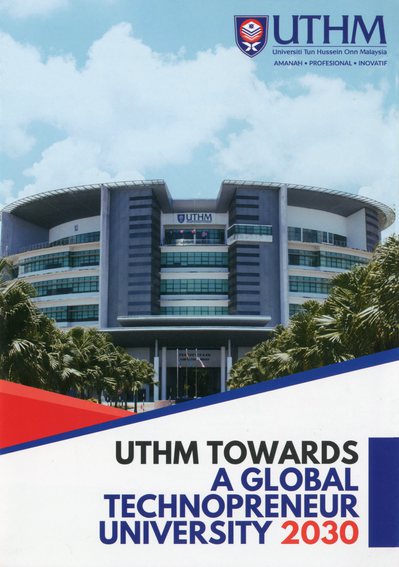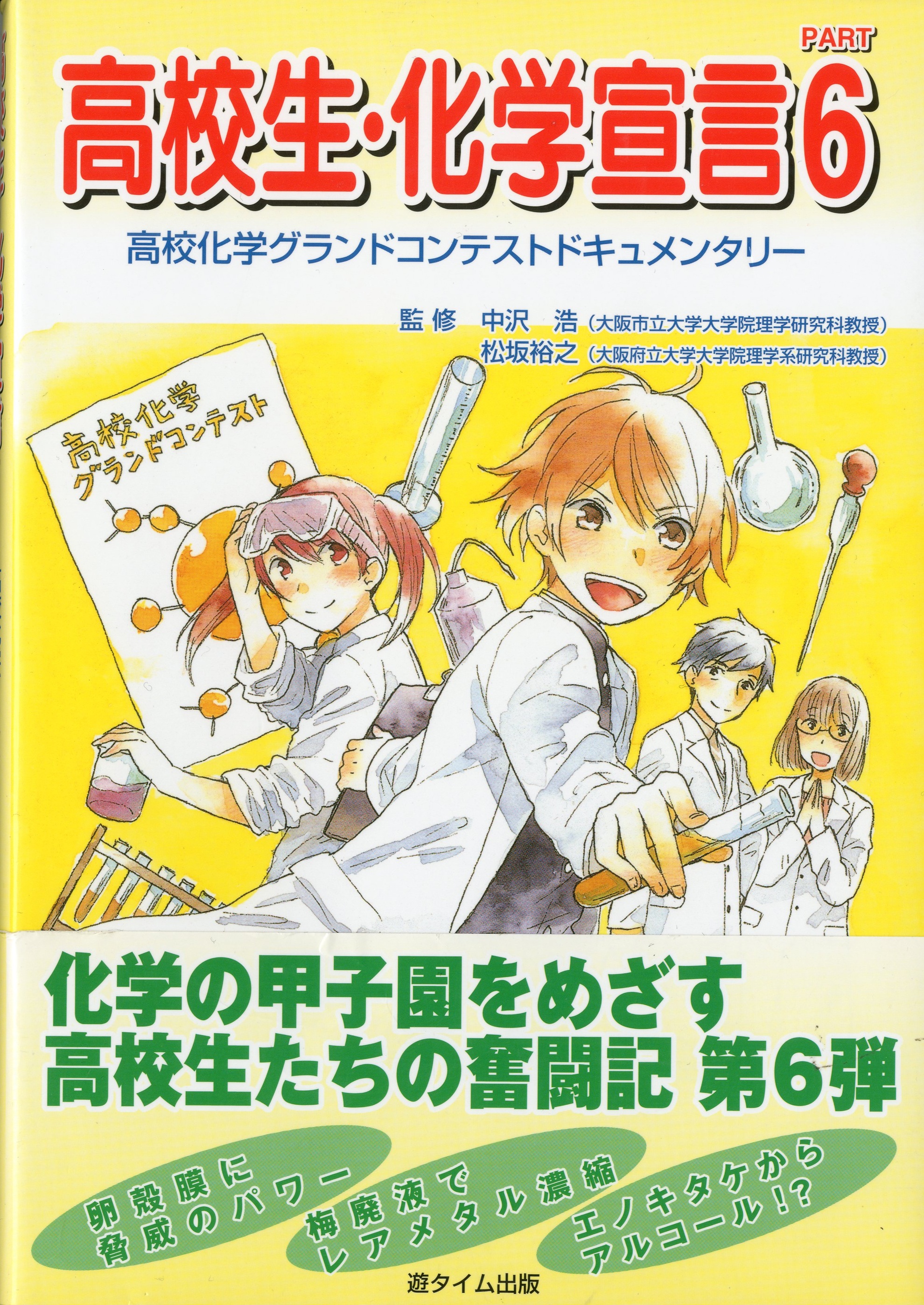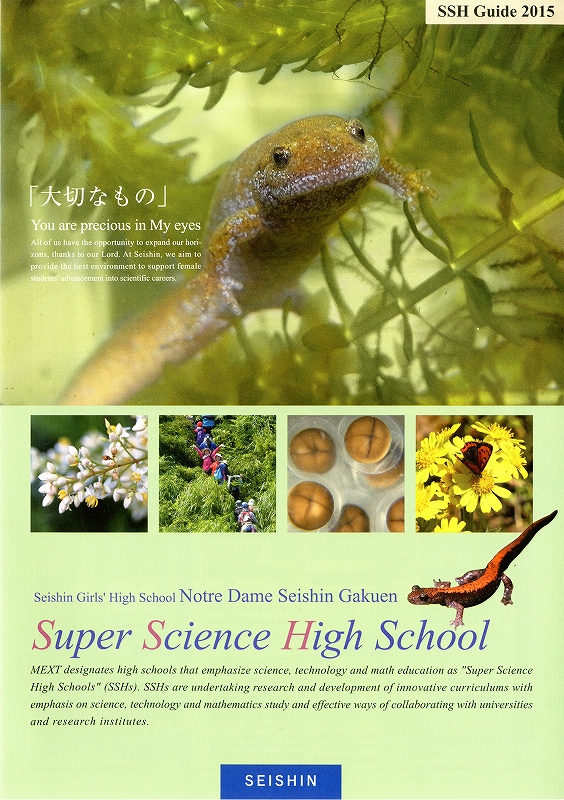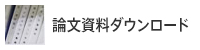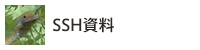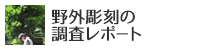グローバルな視点をもち「地球規模の危機管理」を考える人材を育成することを目的に掲げ、生物多様性や生態系保全活動を学ぶ研修先として、多民族・多宗教国家であるマレーシアを選定した。研修内容については、マレーシア国立ツン・フセイン・オン大学(UTHM, ジョホール州)との連携が決定しており、旅行会社の仲介は受けていない。
私は2006年度から2016年度まで岡山県のSSH校であるノートルダム清心学園清心女子高等学校においてSSH主任を務め、科学教育プログラムの一環として環境学習を目的とした海外研修を企画・運営してきた経験がある(清心学園紀要No.15参照)。この経験を踏まえ、山脇学園の文部科学省SSH申請に際しては、学内研究所(山脇有尾類研究所:生徒の科学研究を指導)の企画として海外研修を盛り込んだ。
山脇学園高等学校は現在、研究開発課題「地球市民として行動し、科学・技術者へキャリア選択する女子生徒の育成拠点形成」でSSH指定2年目を迎えている。今年度末(2026年3月、フィリピン)および来年度(2026年8月、マレーシア)に実施予定の海外研修計画が進行中である。具体的な研修内容は、連携しているフィリピン大学ロスバニョス校(UPLB)およびツン・フセイン・オン大学(UTHM)の研究者に提案していただいた候補地を下見のうえ、最終的に決定することにしている。
8月10日深夜、羽田空港を出発し、翌朝6時にクアラルンプール空港に到着した。UTHMまでは自動車で約2時間を要するが、旧知の大学院生が迎えに来てくれた。コロナ禍の影響で海外研修は一時中断され、マレーシアを再び訪れることはないだろうと考えていたため、久しぶりの現地での朝食には懐かしさがこみ上げた。なお、8月31日はマレーシアの独立記念日(1957年、イギリスより独立)であり、滞在中は多くの場所で国旗が掲げられている光景を目にした。