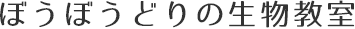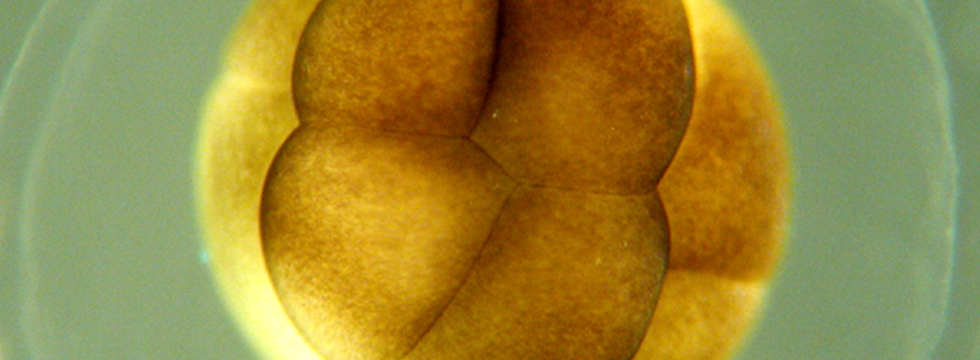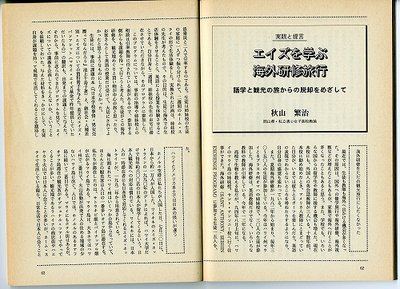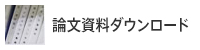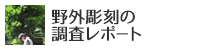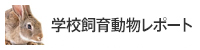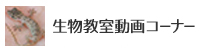正しい知識だけでは、差別はなくならない
エイズという言葉が、突然、社会に重くのしかかってきた時代があった。
テレビや新聞では連日のようにエイズが取り上げられ、「正しい知識を持ちましょう」「恐れる必要はありません」という言葉が繰り返されていた。学校現場でも、エイズは「教えるべきテーマ」として扱われるようになり、性教育の中で取り上げることが半ば当然になっていった。
私自身も、エイズについて学び、生徒に伝える必要性は強く感じていた。しかし、その一方で、どうしても拭えない違和感があった。それは、「正しく理解すれば、差別や偏見はなくなる」という考え方そのものに対する違和感だった。
本当にそうだろうか。
知識さえあれば、人は他者を傷つけなくなるのだろうか。
当時、エイズに感染した人々に対する差別事件が相次いでいた。学校現場でも、感染者やその家族が排除されたり、噂話の対象になったりする事例が報じられていた。パンフレットには「誤解や偏見をなくしましょう」と書かれていたが、その言葉が、どこか空虚に感じられてならなかった。
私は次第に思うようになった。問題は「知らないこと」だけではない。むしろ、「知ろうとしないこと」「他者の立場に立って考えようとしないこと」こそが、差別を生み出しているのではないか、と。
日本におけるエイズ問題には、もう一つ、見過ごしてはならない側面があった。諸外国では、当初、同性愛者を中心に広がった病気として認識されたエイズが、日本では血友病患者への感染から社会問題化したという事実である。非加熱血液製剤によるHIV感染は、明らかに人為的な薬害事件だった。
にもかかわらず、社会の目は冷たかった。「同情すべき感染者」と「自業自得の感染者」を分けるような言説が、当たり前のように存在していた。そこには、「自分は安全な側にいる」という無意識の線引きがあったように思う。
しかし、感染したという事実の前では、理由の違いは本質的な問題ではない。どの感染者も、「死」という現実に直面した一人の人間である。そのことを、教育の場でどう伝えるのか。それが、私に突きつけられた問いだった。
性教育の時間に、私はあえて問いかけるようにした。
「もし、自分の身近な人が感染したら、どう感じるだろうか」
「正しい知識を知っている自分は、差別しないと言い切れるだろうか」
すぐに答えが出る問いではない。沈黙が流れることも多かった。それでも、その沈黙こそが必要なのだと思っていた。知識は一瞬で伝えられるが、他者への想像力は、時間をかけてしか育たない。
エイズをめぐる学習を通して、私は確信するようになった。性教育は、感染予防のためだけの教育ではない。それは、人権教育であり、「生き方」を問う教育なのだということを。
誰かを「危険な存在」として遠ざけるのではなく、「同じ時代を生きる一人の人間」として想像する力。その力を育てることなしに、どれほど正確な知識を教えても、差別は形を変えて繰り返される。
エイズという病気が突きつけたのは、医学的な課題だけではなかった。
それは、私たち一人ひとりが、他者とどう向き合うのかという、極めて根源的な問いだったのだと思う。