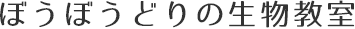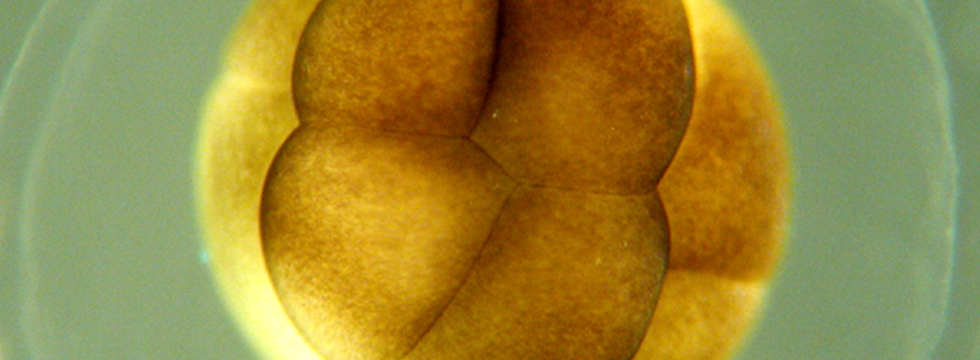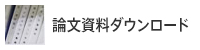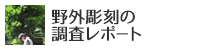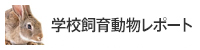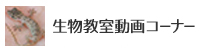高校生と一緒に、性を語れる場をつくった日々
「授業」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、教室で教師が前に立ち、知識を説明する光景だろう。
しかし、私が最も強く「これは教育だった」と実感している時間の一つは、教科書も黒板も使わず、生徒と机を囲んで行った翻訳作業の中にある。
1990年代初め、私は担任していた生徒たちと一緒に、エイズに関する英語の書籍を翻訳するという取り組みを行った。大学受験を控えた時期に、あえてそんな回り道を選んだことを、無謀だと思う人もいたかもしれない。
きっかけは、文化祭だった。
「どうせなら、形に残るものをつくろう」
そんな生徒の一言から、社会問題をテーマにした冊子をつくることになり、その流れの中で、エイズを扱うことになった。やがて、それは一過性の取り組みでは終わらず、高校3年生全体での翻訳プロジェクトへと発展していった。
扱ったのは、SAFER SEX: WHAT YOU CAN DO TO AVOID AIDS という英語のペーパーバックである。英語教師でも医師でもない私にとって、この本を教材として扱うことは、大きな挑戦だった。だが、生徒と同じ立場で学び、分からないことは一緒に調べる。その姿勢で臨もうと決めていた。
翻訳作業は、決して効率的ではなかった。一文一文を読み、言葉の意味を確かめ、日本語としてどう表現すべきかを話し合う。その過程で、必然的に「性」に関する言葉と向き合うことになった。
「この言葉、どう訳せばいいんでしょう」
「日本語にすると、きつくなりすぎませんか」
そんなやり取りが、自然に交わされた。性について語ることに、最初は戸惑いもあったはずだ。それでも、生徒たちは驚くほど率直だった。ふざけることもなく、必要以上に構えることもなく、目の前の言葉と誠実に向き合っていた。
あるとき、"bisexual"という単語の訳をめぐって議論になった。市販の翻訳書では、差別的なニュアンスを含む言葉が使われていたが、生徒たちは即座に違和感を示した。
「それは違うと思います」
理由を聞くと、「この言葉だと、人を傷つける気がする」という答えが返ってきた。
その瞬間、私は強く思った。性教育で本当に大切なのは、知識の量ではない。言葉の選び方一つに、他者への想像力が宿る。その感覚こそが、人権の感覚なのだと。
翻訳作業が進むにつれ、教室の空気は、通常の授業とはまったく異なるものになっていった。質問は増え、沈黙も増えた。沈黙は、逃避ではなく、考えている時間だった。父親と一緒に翻訳に取り組んだ生徒もいた。英語の教師に相談に行った生徒もいた。学習は、教室の外へと自然に広がっていった。
後に、私たちが翻訳した本は、日本語版として出版された。完成度という点では、私たちの直訳は、決して洗練されてはいなかっただろう。それでも、私は確信している。あの翻訳作業で生まれた文章には、生徒一人ひとりの「考えた跡」が刻まれていた。
翻訳が終わった後、協力してくれた英語の教師が、こんなことを言ってくれた。
「性に関する言葉を、こんなに自然に話せるようになるとは思わなかった」
性は、社会の中で長い間、抑圧されてきたテーマである。猥雑なものとして扱われるか、沈黙されるか、そのどちらかであることが多かった。しかし、翻訳という共同作業を通して、性は「語ってよいもの」「考えてよいもの」として、教室の中に居場所を得た。
この経験を通して、私は改めて確信した。
性教育とは、性について語る訓練ではない。
他者を傷つけない言葉を選ぼうとする、その姿勢を育てる教育なのだ。
翻訳という遠回りは、結果として、生徒と私の間に、深く静かな信頼を育ててくれた。
それは、どんな「正しい説明」よりも、雄弁だった。