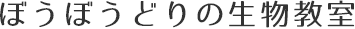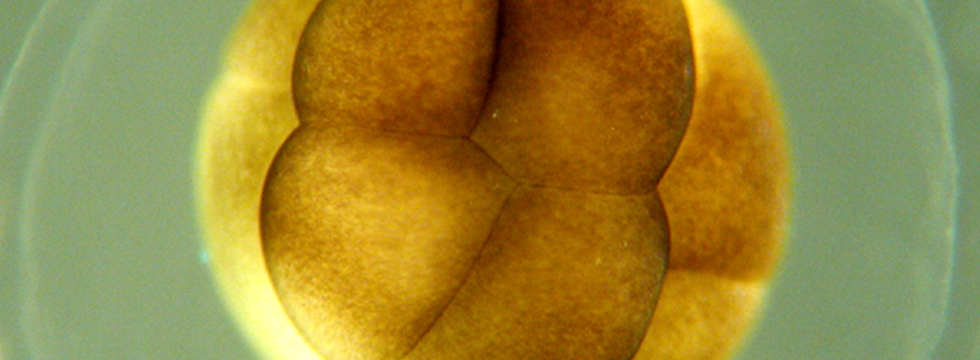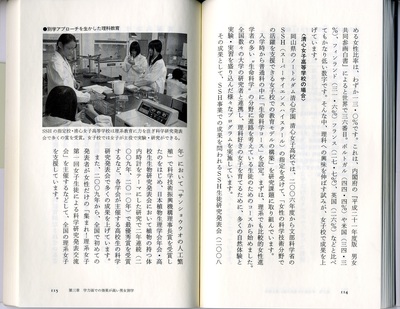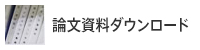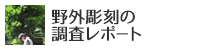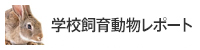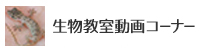リーダーシップが育つ場として
「今の時代に、女子校は必要なのでしょうか」
1990年代半ば以降、学校関係者の間で、何度となく耳にした問いである。少子化が進み、共学化や校名変更、コース制導入といった改革が次々に行われる中で、女子校は「時代遅れの存在」と見なされることも少なくなかった。
実際、岡山県内の私立高校24校のうち、女子校は2校のみとなった。全国的に見ても、女子校はもはや少数派である。男女共同参画が叫ばれる社会において、「男女を分ける学校」に意味があるのか――その問いは、決して軽いものではなかった。
私自身も、最初から明確な答えを持っていたわけではない。だが、長年女子校で教壇に立ち続ける中で、少しずつ見えてきたものがあった。
それは、女子校という場では、「誰が前に立つか」を女子自身が引き受けざるを得ない、という事実である。
生徒会の会長も、副会長も、クラスの代表も、実験や実習のリーダーも、すべて女子である。そこに「男子がやる役割」は存在しない。必然的に、意見を言う、まとめる、決断する、責任を取るといった経験を、女子生徒自身が積み重ねていくことになる。
共学校では、無意識のうちに「前に出る役割」を男子が担い、女子がそれを支える構図が生まれることがある。もちろん、すべての共学校がそうだと言うつもりはない。しかし、社会全体に根強く残るジェンダー意識が、学校という場にも影を落としていることは否定できない。
女子校では、その構図が成立しない。
やらなければならないから、やる。
誰かが代わってくれるわけではないから、自分が引き受ける。
その積み重ねが、女子生徒の中に、静かな自信を育てていくのを、私は何度も目にしてきた。
一方で、日本社会は、少子化と人口減少という大きな課題に直面している。女性が子どもを産まなくなったから少子化が進んだ、という単純な説明がなされることもあるが、問題はそんなに単純ではない。ライフスタイルの変化、社会制度の遅れ、働き方の問題など、要因は複雑に絡み合っている。
ただ一つ確かなのは、女性の生き方が、社会のあり方そのものを変えつつあるという事実である。にもかかわらず、日本では、科学技術分野をはじめ、意思決定の場に立つ女性の割合が依然として低い。
理科教員として現場に立つ中で、私は強い違和感を覚えてきた。
なぜ、理系を志す女子はこんなにも少ないのか。
その原因は、本人の能力や意欲ではなく、育ってきた環境にあるのではないか。
もし、無意識のうちに「理系は男子のもの」「リーダーは男性」というメッセージを受け取り続けてきたとしたら、女子が一歩引いてしまうのも無理はない。だからこそ、女子校という環境が持つ意味は、今なお失われていないと私は考えている。
女子校は、女性を特別扱いする場ではない。
むしろ、「最初から主役であることを求められる場」なのである。
この環境を生かして、女子が自分の力を試し、失敗し、再び立ち上がる経験を積み重ねることができれば、それは将来、どのような進路を選んだとしても、大きな支えになるはずだ。
私が後に、生命科学コースや理系進学支援に力を注ぐようになった背景には、こうした女子校の現場での実感があった。女子校だからこそできる教育がある。その可能性を、私は信じたかったのである。
女子校は、過去の遺物ではない。
これからの社会を担う力を育てる、一つの選択肢なのだと思っている。