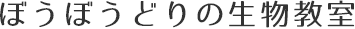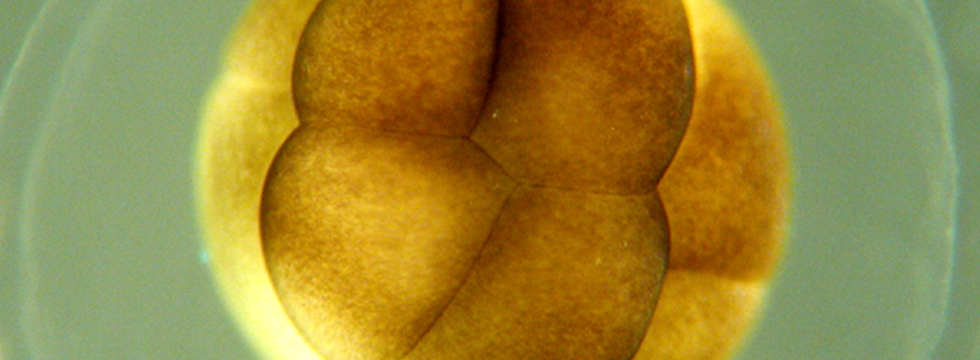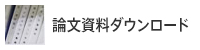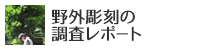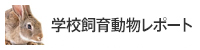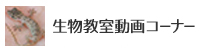教育者として、何を残せたのか
2016年11月、私は1983年から勤務してきたカトリック系中高一貫女子校を退職した。
その翌月、長く学園を導いてこられた理事長、シスター渡辺和子が逝去された。
一つの時代が、静かに幕を閉じた。
そう感じた。
シスター渡辺の著書『置かれた場所で咲きなさい』は、多くの人に読まれた。その言葉に救われた人も少なくないだろう。だが、私はこの言葉を、単なる励ましとしてではなく、問いとして受け止めてきた。
――人は、本当に「置かれた場所」で咲けているのだろうか。
――その場所は、問いを許しているだろうか。
振り返れば、私の教員生活は、問いの連続だった。
若い教師だった頃、教室に立つことの難しさに戸惑い、学級通信を書き続けることで、生徒との距離を測り続けた。性教育に偶然関わり、管理のための教育への違和感を抱いた。エイズという社会問題を通して、知識では埋められない差別と向き合った。翻訳という遠回りの授業で、言葉の重さと他者への想像力を学んだ。
授業「生命」をつくったのも、答えを教えたいからではなかった。
むしろ、「答えのない問いに、耐えられる場」を、学校の中につくりたかったからである。
女子校という現場で、生徒が前に立ち、決断し、失敗し、また立ち上がる姿を見てきた。理系に進むかどうかよりも、「自分で選んでよい」と思えることの方が、はるかに大切だと感じるようになった。SSHや生命科学コースは、その延長線上にあったにすぎない。
こうして書き連ねてみると、私は「何かを教えた教師」というより、「問いのそばに立ち続けた一人の大人」だったのかもしれないと思う。
教育者として、何を残せたのか。
この問いに、明確な答えを持っているわけではない。
知識は、やがて古くなる。
制度は、時代とともに変わる。
だが、「自分で考えてよい」「問いを持ってよい」という感覚は、長く人の中に残る。
もし、かつての生徒の中に、
――あのとき、立ち止まって考えてよかった
――自分の言葉で選んでよかった
そう思える瞬間が一つでもあるなら、それで十分なのかもしれない。
教育は、成果が見えにくい仕事である。
すぐに花が咲くこともあれば、何年も経ってから芽を出すこともある。教師がそれを目にすることは、ほとんどない。
それでも、問い続けることは、やめられない。
問いを手放した瞬間、教育は、管理や操作に変わってしまうからだ。
私は、もう教室に立ってはいない。
しかし、問いは、今も私の中にある。
置かれた場所で、問い続けること。
それが、私なりの「咲き方」だったのだと思っている。
この連載が、誰かにとって、
自分の置かれた場所を、少し違った角度から見つめ直すきっかけになれば、
それ以上のことは望まない。
問いは、これからも、あなたの側にある。